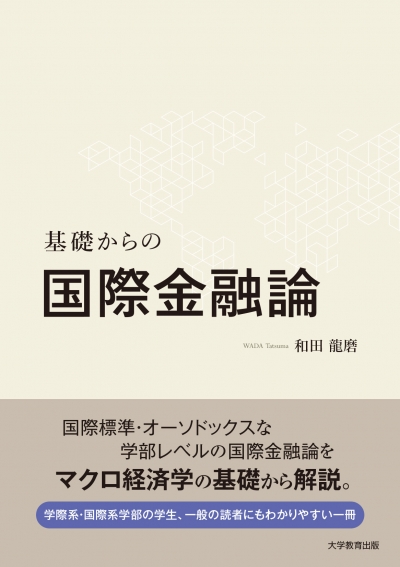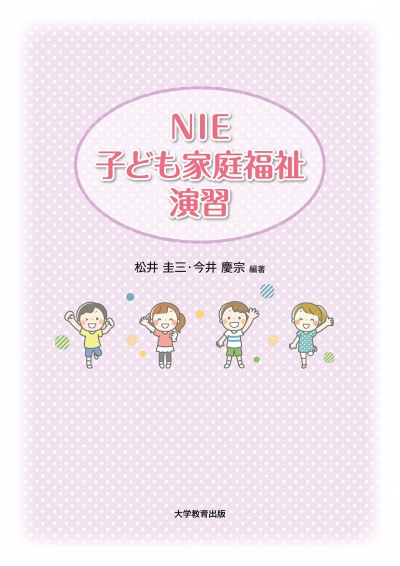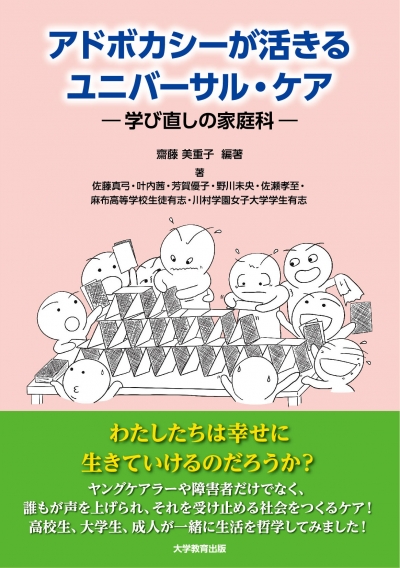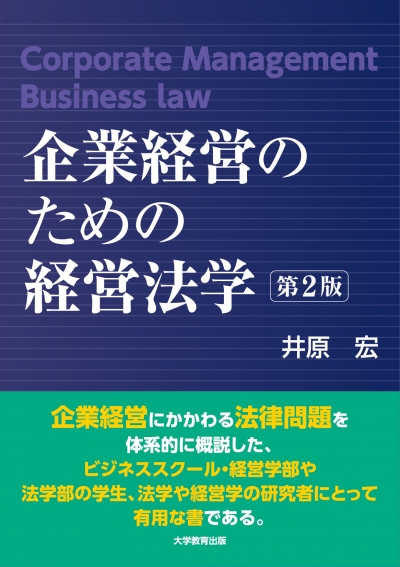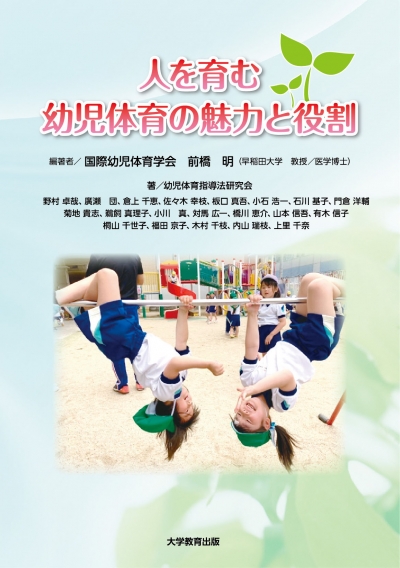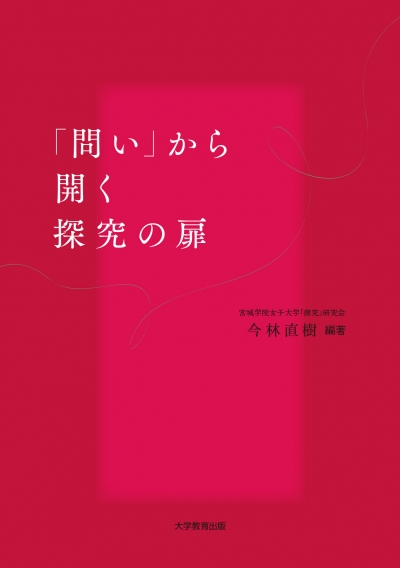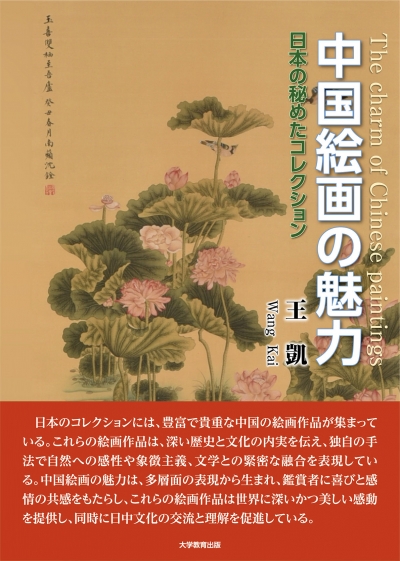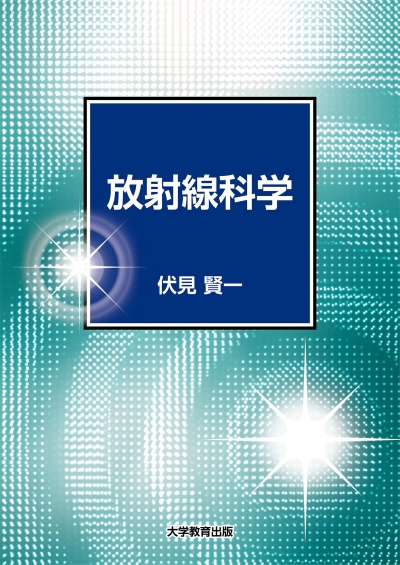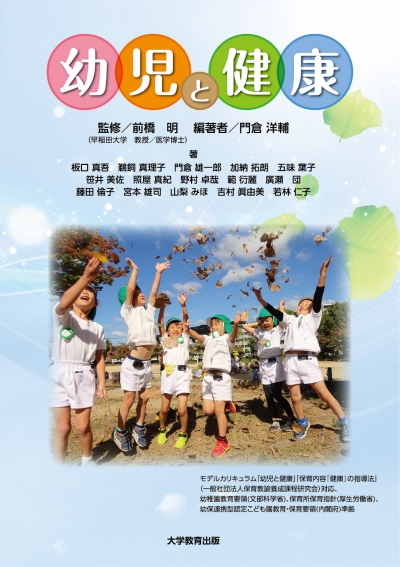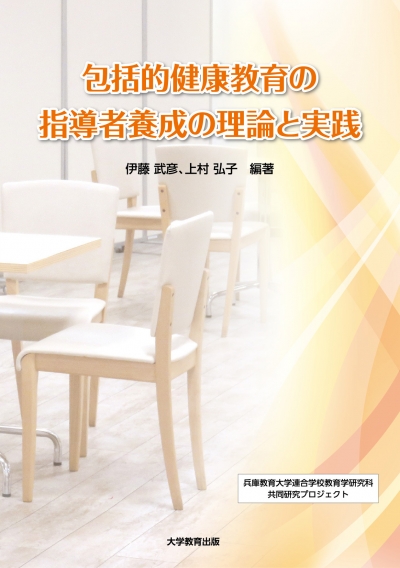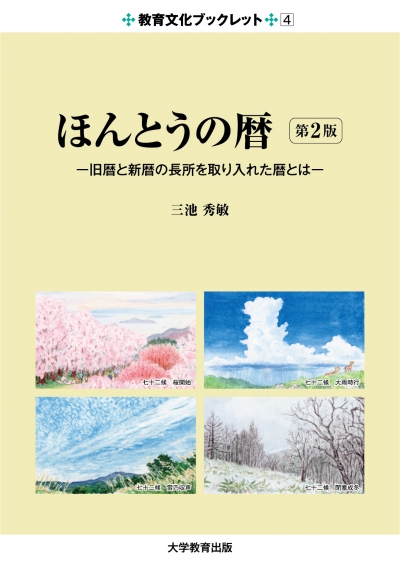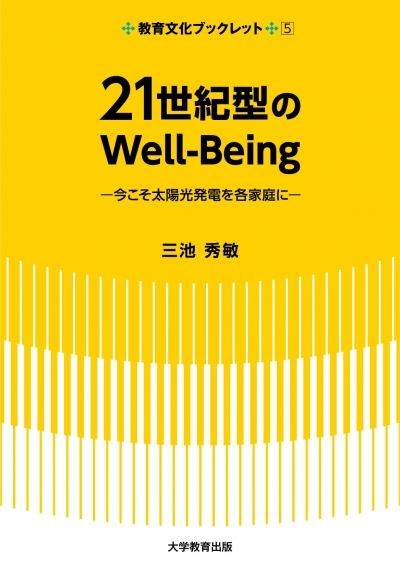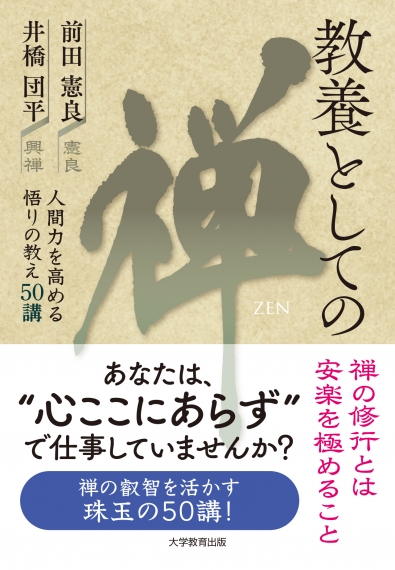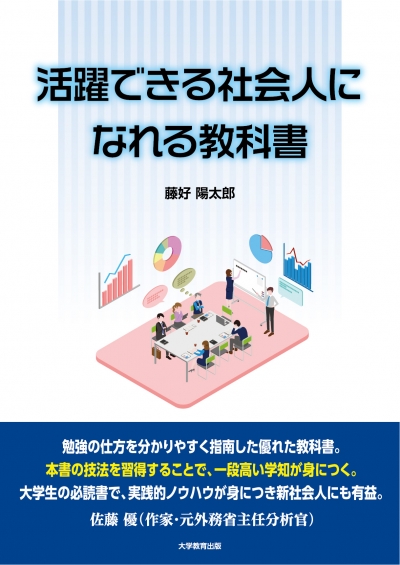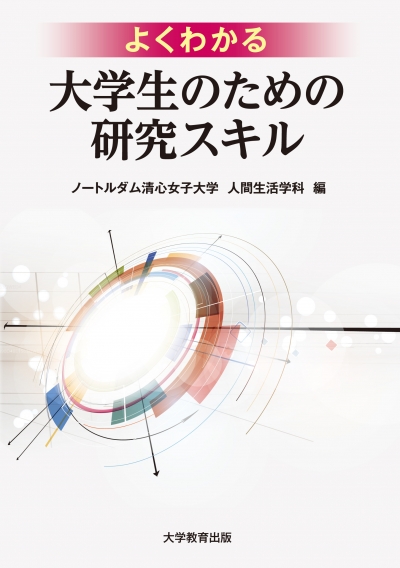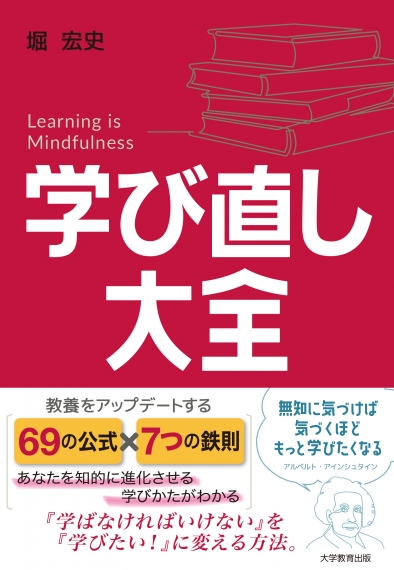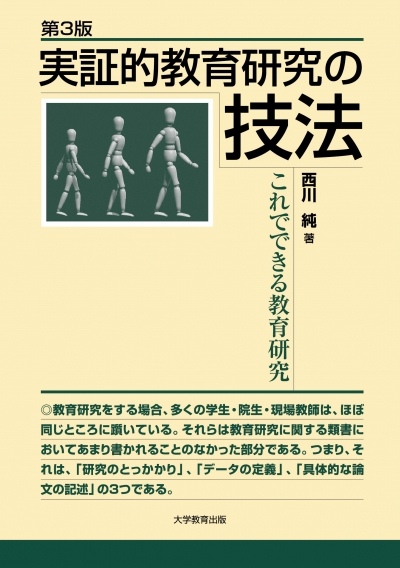- 2024/04/22 付加価値は新たな創造 森脇恵美、塚口伍喜夫
- 2024/04/22 なぜ生命倫理なのか 朝倉輝一、小館貴幸、近藤弘美、米田 祐…
- 2024/04/22 活躍できる社会人になれる教… 藤好陽太郎、横田詞輝
- 2024/04/22 国際事業戦略Ⅰ 井原 宏
- 2024/04/22 公教育と教育行政 改訂第2… 曽我 雅比児
- 2024/04/30 教養としての禅 前田憲良、井橋団平
- 2024/05/01 聖母の平和と我らの戦争 晏生莉衣
- 2024/05/10 高大接続と文章教育 中井 仁
- 2024/05/30 最新 生徒指導論 改訂版 原田 恵理子、森山 賢一
- 2024/05/30 外あそび用語集 前橋 明
-
2024年02月21日
メディア掲載
- NHK「クローズアップ現代」にて報道❕
新刊 『これからの地方創生のシナリオ』 で扱うMaasプロジェクト「ノッカル」を
NHK「クローズアップ現代」(2月14日放送分)で取り上げていただきました。
国家戦略の1つの重要な要素と位置づけられる 「公共交通の維持」。
日本社会を持続可能なものとするための 『ほんとうの地方創生』 のヒントを本書で読み解けます!
https://plus.nhk.jp/watch/st/g1_2024021412049?s_page=web_watch%3Ast%3Ag1_2024021412049#openIosStore
-
2024年02月21日
メディア掲載
- 書評掲載のお知らせ
『新英語教育 』3月号(出版社:高文研)に『英語授業「主体的・対話的で深い学び」を高めるために』高橋昌由(たかはし まさゆき)編著:阿部慎太郎 著/溝畑保之 著/森田琢也 著/岡﨑伸一 著/坂本彰男 著/田中十督 著/米田謙三 著が書評として紹介されました。本書は、理論と実践の両方を網羅した実用的な一冊となっており、英語教育に携わる方にとっての必携書としてご活用くださいますと幸いです。
-
2024年02月15日
メディア掲載
- 書評掲載のお知らせ!
『持続可能なキャリア 不確実性の時代を生き抜くヒント』(北村 雅昭先生 著)
2月15日付で、労働新聞社様ホームページ【書評】コーナーにてとり上げていただきました。
選者の「法政大学大学院 政策創造研究科 教授 石山 恒貴先生」の深い洞察と鋭い視点によって
高い評価をいただきました。 誠にありがとうございます!
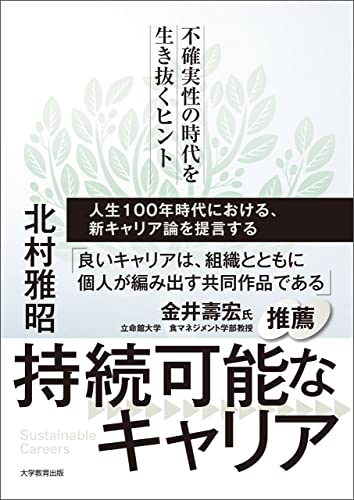
-
2024年01月30日
メディア掲載
- 全国商工新聞1月22日号に掲載されました
岡山大学名誉教授小松泰信先生の著書『農ある世界と地方の眼力6 令和漫筆集』が、全国商工新聞1月22日号の「おすすめの一冊」欄で紹介されました。
JAcom&農業協同組合新聞コラムに連載された記事を出版。22年度の出来事を「地方」と「農ある世界」の視点で、記録と記憶に残る絶妙な辛口コメント。
-
2024年01月05日
メディア掲載
- 山陽新聞に掲載されました
2023年12月28日付の山陽新聞朝刊6面に「農ある世界と地方の眼力6 令和漫筆集」が掲載されました。
本書は、JAcom・農業協同組合新聞のコラム「地方の眼力」に掲載された45編からなる第6弾で、農業・農家・農村・農協といういわゆる「農ある世界」を巡る状況についてのウィークリー・クロニクルである。
-
2024年01月05日
お知らせ
- 新年のご挨拶
あけましておめでとうございます。
旧年中は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
-
2023年12月25日
講習会
- 出版記念ウェビナー 『韓流UX設計アプローチで行う、Webサイトの分析から改善まで』 ご案内
Data-driven UX 出版記念Webセミナー が開催されます。
●日 時:2024年1月10日(水)15:30-16:30
●参加費:無料
データドリブンへの関心が高まっている中、UXデザイナー/プロダクトマネージャー・サービス担当の方はもちろん、Webサイトに関わるすべての方に参考になる内容となっております。
きっと、あなたのビジネスに役立つセミナーです。
ぜひとも、以下からご参加ください!
-
2023年12月20日
お知らせ
- 冬季休業(年末年始)のお知らせ
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
弊社では2023年12/29(金)~2024年1/4(木)まで冬季休業(年末年始)とさせていただきます。
ご迷惑をおかけいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
メールでのお問い合せは、常時受け付けています。
-
2023年11月21日
メディア掲載
- 『どんな子どもも活発になる運動ASOBI指導』がメディアで紹介されました
2023年10月20日に発売しました『どんな子どもも活発になる運動ASOBI指導』がメディアで紹介されました。
メディア紹介媒体は、以下になります。
■愛媛新聞11月19日朝刊
■愛媛経済レポート11月6日分
■松山商工会議所 所報11月号
運動に対して苦手意識を持っている子は、どんな子か。「あそび」の力によって運動に苦手意識が強い子が活発に参加するようになった事例を交えて、あそびの価値やどんな子も活発になる「あそび」プログラムを紹介した本です。
-
2023年10月23日
メディア掲載
- 日本経済新聞(10月11日)に掲載されました
◆『電気パンの歴史・教育・科学』の紹介が、日本経済新聞(10月11日)に掲載されました。
電気パンは、戦前の陸軍で開発された「炊飯自動車」に起源があるとのことで、戦後は教育に活用されてきました。パン生地には電解質の食塩とベーキングパウダーが含まれるため、電流が流れてジュール熱が発生し、それによる熱分解で二酸化炭素が発生して生地が膨らむ。
これは、エネルギー変換、化学反応等で理科の学習事項をカバーしているため、教育活動に活用されてきました。現在は、「電極式調理」に活用されており、電気パンの歴史をたどった本である。
-
2023年09月08日
お知らせ
- 「学びの森」 最新記事のご案内
わが社のホームページでは、有識者による知と教養のWeb本「学びの森」を連載形式で更新中です。
「キになる視点」と「キほんのWORD」の2冊です。
今年の日本学校教育学会賞を受賞された藤江玲子先生による「高校生のドロップアウト」に関する
連載記事の最終回を掲載。 ぜひ、学びの森の散歩へお越しください!
-
2023年09月06日
講習会
- 『2040年からの提言―SDGsネイティブの作る未来―』の著者・筒井隆司氏による講演があります。
1. 9月20日(水):SMBCコンサルティングの経営者セミナー(会員限定)にて
2. 10月20日(金):法政大学大学院・経営研究科の院生(MBA)対象として●大学の教員や学生向けの講演(対面・zoom)も企画可能ですのでお気軽にご相談ください。
-
2023年09月05日
メディア掲載
- 『植物の知恵 ― その仕組みを探る ―』 書評が掲載されました
「生物教育」第64巻 第3号(通巻246号)(一般社団法人日本生物教育学会、令和5年8月1日発行) において、植物生理化学会 編、長谷川宏司 監修『植物の知恵 ―その仕組みを探る― 』の書評が掲載されました。「『植物の環境応答』について……〈略)……新しく知ることも多く、科学物質の裏付けがあってはじめて説得力をもつことも理解できた」(評者:早崎博之氏のことば)。本書は、厳しい環境下でも生き抜くために植物が具備している “知恵”の仕組みを各分野のレジェンドたちが解説したものです。
-
2023年09月01日
受賞
- 2023年度『日本学校教育学会賞』
藤江玲子先生著「高校生のドロップアウトの予防に関する研究 ―子どもたちが幸せに生きることのできる社会―」が、今年度の『日本学校教育学会賞』を受賞しました!
高校教育の現場と、公表されているデータには乖離があります。調査・研究に基づき、心理と教育を結ぶ視点から提言した一冊。ぜひご一読ください。
-
2023年08月28日
お知らせ
-
2023年08月04日
お知らせ
- 夏季休業のお知らせ
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
弊社では2023年8月11日(金)~2023年8月16日(水)まで夏季休業とさせていただきます。
ご迷惑をおかけいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
メールでのお問い合せは、常時受け付けています。
-
2023年07月26日
お知らせ
- 「学びの森」 最新記事を掲載しました!
わが社のホームページでは、有識者による知と教養のWeb本として「学びの森」を連載形式で更新中。
「キになる視点」と「キほんのWORD」の2冊です。
今月のテーマは、高校生のドロップアウトに関する記事ですが、このほかにもたくさんアップしております。
ぜひ、学びの森を散歩してみてください!
-
2023年05月25日
メディア掲載
- 尚絅学院大学のHPで紹介されました
弊社から刊行しました書籍『植物の知恵―その仕組みを探る―』 が、ご執筆くださった田幡先生の勤務校 尚絅学院大学のHPで紹介されました。
植物研究の世界的レジェンドたちが、基本的事項から最新の研究成果、動向までを分かりやすく解説しています。
-
2023年05月11日
メディア掲載
- メディア掲載(福祉新聞)のお知らせ
福祉新聞社発行の福祉新聞5/2発行分において弊社書籍『急ごう介護の国際化を』の広告(3段1/2面)を掲載いたしました。
介護業界が直面する国際化への展望を実体験を基に解説しています。介護福祉事業者の必携本です。
-
2023年04月21日
お知らせ
- GW休業のお知らせ
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
弊社では2023年5月3日(水)~5月7日(日)までGW休業とさせていただきます。
ご迷惑をおかけいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
メールでのお問い合せは、常時受け付けています。